以前、「原材料表をチェック!加工食品によく使用される健康を害する添加物ワースト5」という記事でも特集した、多くの加工食品に含まれている食品添加物。食品が美味しそうに見えたり、長持ちしたり、風味を出したりと、使用されている理由はさまざまです。健康志向のgeefeeの読者の中でも常に気にしている人も多いことと思います。
この食品添加物は、各国によって禁止/制限のラインはさまざま。消費者側から見ると、できれば厳しいルールのもとになるべく体に悪いとされる添加物が入っていない食品を生産してもらいたいものですが、日本は他国に比べて基準が緩い部分が多々あります。今回は、他国では厳しく規制されているのにも関わらず、日本では規制の緩い食品添加物にフォーカスを当ててみました。
赤色2号
合成着色料である赤色2号は、お菓子や清涼飲料水やアイスなど、多くの食品に使用されていますが、1970年頃から発ガン性の疑いがもたれています[#]Agricultural Marketing Service (United States Department of Agriculture), October 14, 2005, pp. 1 and 7, retrieved August 15, 2014 。また、ラットを使った研究でも悪性腫瘍の発生率が統計的に有意に増加しています[#]Omaye, Stanley T. (2004). Food and Nutritional Toxicology. CRC Press LLC. p. 257. ISBN 0-203-48530-0. 。子供は鮮やかな色の食べ物にそそられるため、駄菓子などでよく使用されています。
この赤色2号は、日本では、ADI(一日摂取許容量)を0.5mg/kg体重/日[#]“食品添加物の制度の概要 ~リスク管理について~” n.d. Accessed March 2, 2020. https://www.fsc.go.jp/koukan/risk-workshop_ooita_211201/risk-workshop_oo.... 。使用規制国のEuの場合、ADIが0.15 mg/kg体重/日[#]“食品安全関係情報詳細.” n.d. Accessed March 2, 2020. http://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu03170150149. となりますので、例えば20kgの6歳児の場合、
日本:1日で1g
Eu:1日で0.3mg
まで摂取して良いということ。親御さんは、原材料に赤色2号が表示されていたら是非ご注意を。
その他、赤色40号、赤色102号なども同類。特に、赤色40号は、ラットを使った研究とはいえ、繁殖成功率を低下させ、脳の重量を減らすことが分かっています[#]pubmeddev, and Et al Vorhees CV. n.d. “Developmental Toxicity and Psychotoxicity of FD and C Red Dye No. 40 (allura Red AC) in Rats. - PubMed - NCBI.” Accessed March 2, 2020. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6636206. 。
他国の使用状況[#]https://www.fsc.go.jp/sonota/factsheet-kbro.pdf
[禁止国]
アメリカ、カナダ、韓国、UAE[#]Office of Regulatory Affairs. 2020. “CPG Sec 587.200.” U.S. Food and Drug Administration. October 2, 2020. http://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/.... [#]“[食品添加物規制調査 UAE].” n.d. Accessed March 2, 2020. https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2016/aef99e59a3163ad7/rpU....
[規制国]
EU
臭素酸カリウム
強力な酸化剤である臭素酸カリウムは、日本では小麦粉処理剤として使用が認められています。パンを生産する際に、主にパン生地のふくらみ方や食感などの改良目的として発酵中に使用されることがあるのです。国際がん研究機関(IARC)では、人に対して発ガン性の恐れがあるとされているにも関わらず、日本ではパンの製造で使用が認められていますが、
1.添加量は30ppm以下
2.最終製品での残留は禁止
とされています。特に2.については、臭素酸カリウムは加熱時に分解されるため、製品化された段階では検出されないケースがほとんど。そのため、残存が検出されない場合は、使用していても表示義務は特にないのです。
他国の使用状況[#]“[臭素酸カリウム - 食品安全委員会].” n.d. Accessed March 2, 2020. https://www.fsc.go.jp/sonota/factsheet-kbro.pdf.
[禁止国]
EU、カナダ、ナイジェリア、ブラジル、スリランカ、中国など[#]“[臭素酸カリウム - 食品安全委員会].” n.d. Accessed March 2, 2020. https://www.fsc.go.jp/sonota/factsheet-kbro.pdf.
[規制国]
イギリス(パン製造において)、中国(小麦粉処理剤として小麦粉での使用)米国では表示義務あり
食品中に発生してしまうことがある有毒物質「クロロプロパノール類」の体への影響
食品を製造する過程で、もともと原料に含まれている脂質から意図せず生産されてしまう物質である「クロロプロパノール類」。これは醤油の製造過程で発生することがよく知られています。動物実験では、この物質が、腫瘍、腎臓の損傷、繁殖成功率の低下を引き起こす要因となっていることが分かっています[#]“[3-MCPD: A Worldwide Problem of Food Chemistry].” n.d. Accessed March 2, 2020. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10408398.2013.829414. EUでは、醤油1kgあたり0.02mgまで、アメリカでは、1kg辺り1mgまでを上限として設定していますが、実際に欧米などの市場に出回っている醤油から大幅に制限値を超えた「クロロプロパノール類」が見つかり、製品リコールの騒ぎにもなっています[#] “3‐Chloropropane‐1,2‐diol (3‐MCPD) in Soy Sauce: A Review on the Formation, Reduction, and Detection of This Potential Carcinogen ” n.d. Wiley Online Library. Accessed March 2, 2020. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1541-4337.12120. 。
では、醤油大国日本ではどうでしょうか?
日本では農林水産省によると、「消費者の方々の健康への悪影響の程度、食品の品質を考慮した上で、無理なく達成可能な範囲でできる限り食品中の濃度の低減に努める必要があります。」といった程度で、特に規制はされていません。そこで消費者自らがクロロプロパノール類から身を守る必要があるのですが、どのようにすればよいのでしょうか?そこで注目すべきは「アミノ酸液」という原材料。国産の醤油の大部分はアミノ酸液を使用しない本醸造方式という製法で作られており、これらの醤油からはクロロプロパノール類が検出されていません。一方、アミノ酸液が使用される混合醸造方式や混合方式と呼ばれる製法の醤油にはクロロプロパノール類の含有濃度が高い傾向にあることが確認されています[#]“[調味料中のクロロプロパノール類含有実態調査の結果について(平成18年度)].” n.d. Accessed March 2, 2020. https://www.maff.go.jp/j//syouan/seisaku/c_propanol/pdf/h18_report.pdf. 。スーパーなどに並ぶ醤油の原材料に「アミノ酸液」と表記された醤油を見かけたら要注意です。

農薬の規制も緩い日本
柑橘類やバナナなどに使用され、肝臓に影響を与え、機能障害や組織損傷を起こす可能性のあるイマザリルやチアベンダゾール[#]“[ハザード概要シート(案)(イマザリル)].” n.d. Accessed March 2, 2020. https://www.fsc.go.jp/sonota/hazard/noyaku_19.pdf. 。これらの農薬は、国内では農薬として使用することが禁止されているにも関わらず[#]“[ハザード概要シート(案)(イマザリル)].” n.d. Accessed March 2, 2020. https://www.fsc.go.jp/sonota/hazard/noyaku_19.pdf. 、食品添加物(防腐剤)としては使用可能となっているという、消費者側からは納得しづらい状況になっています。特に、イマザリルは、農薬として日本では認可が下りていないにも関わらず輸入規制はされておらず、輸入規制を緩和するために食品添加物指定がされたとも言われています。海外から輸入されるフルーツに、収穫後にこれらの物質を振りかけ、輸送中にカビが発生しないようにしていることは良く知られています。したがって、輸入されたオレンジやレモンを皮ごと使用するのは絶対にやめるべきなのです。
また、その逆で、EUや一部のアメリカでは使用が禁止・制限されているにも関わらず、日本では残留基準値の緩和が行われているどころか、新規の承認も行われているネオニコチノイド農薬。
このネオニコチノイドでコーティングされた大豆やトウモロコシやヒマワリの種子は、いわば殺虫剤に包まれた種子のようなもの。害虫には毒性が強くヒトには安全とされていましたが、最近では、ヒトへの神経発達障害の影響が懸念され、特に、子供の発達にも悪影響はあることが分かっています[#]“[新農薬ネオニコチノイド系農薬のヒト・哺乳類への影響].” n.d. Accessed March 2, 2020. http://www.asahikawa-med.ac.jp/dept/mc/healthy/jsce/jjce21_1_46.pdf [#]“[Effects of Neonicotinoid Pesticide Exposure on Human Health: A Systematic Review ].” n.d. Accessed March 2, 2020. https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/ehp515. 。
また、ミツバチの大量死や失踪などによる昆虫の生態系への悪影響がアメリカでは大きな問題になっています。ミツバチにとってDDTの1000倍の毒性があると言われている強力な神経毒であるネオニコチノイドは[#]“Toxic Acres Study.” n.d. Friends of the Earth. Accessed March 2, 2020. https://foe.org/toxic-acres/. は、送粉者であるミツバチの生態系を破壊し、また、土壌や環境にも多大な悪影響を与えています。
有害な農薬が使用されている農作物は輸入され、尚且つ自国でも使用制限が緩い先進国は日本だけかもしれません。

日本は先進国の一員であるにもかかわらず、健康に関する規制においてはまだまだ発展途上の側面があると言えます。海外で健康に悪影響を与えると規制されている物質が、メーカー側の都合などで野放しにするというのは我々消費者から見ると納得できませんよね。健康に有害な物質に対する規制が世界標準に追いつくまでは、日本の消費者は、原産地や原材料などをしっかり確認し、自分の身は自分で守るという姿勢で食生活を送っていく必要があるのです。


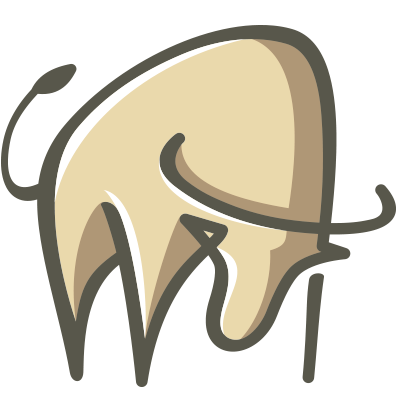


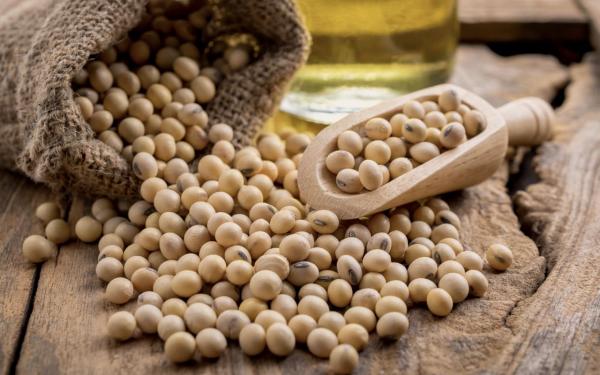



 中級
中級 
 初級
初級 






コメント
コメントを追加